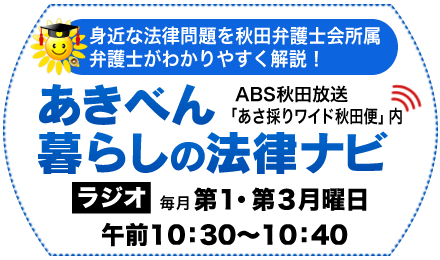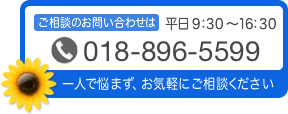再審法の改正を求める決議
当会は、現行の再審制度の問題点を踏まえ、国に対し、刑事訴訟法「第四編 再審」の規定に関し、以下のとおり改正することを求める。
1 証拠開示制度を新設し、検察官に、捜査機関が保管するすべての公判未提出証拠を記載した証拠目録の作成と開示を義務付けること、およびすべての証拠の開示を義務付けること
2 再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止すること
以上のとおり決議する。
2023年(令和5年)10月24日
秋 田 弁 護 士 会
決議の理由
第1 無罪推定の原則と再審手続の意義
個人の尊重を最高の価値として掲げる日本国憲法の下では、無辜の人間を罰することは絶対に許されない。日本国憲法31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定し、この趣旨を受け刑事訴訟法336条は、「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。」と定め、無罪推定の原則を規定している。
1975年、最高裁判所は、再審手続においても上記の無罪推定の原則が適用されるとの判断を示した(いわゆる白鳥決定。最高裁昭和50年5月20日決定)。かかる決定を受け、1980年代には、財田川事件、免田事件、松山事件、島田事件といういわゆる「四大死刑冤罪事件」のいずれにおいても、再審の結果、死刑判決が破棄され、再審手続における人権擁護の機運は大いにその高まりを見せた。
その後、1990年代において、榎井村事件を除き再審無罪判決が下されない状況が続いたものの、2010年に足利事件において再審無罪判決が下されたのを皮切りに、布川事件、東電OL殺人事件、東住吉事件、松橋事件など、再審手続を経て無罪判決が下された事件が再びみられるようになっている。
このような中で、審理の長期化をはじめ、現行の再審制度が抱える様々な問題点が再び顕在化し、再審手続の見直しを求める声が高まっている現状にある。
第2 現行制度の問題点と法改正の必要性
現行の再審制度には問題とされるべき点が多々あるが、大きく2つの点を挙げることができる。それは、証拠開示規定の不備と、再審開始決定に対して検察官の不服申立てを許容する規定である。
1 証拠開示規定の不備
⑴ 再審規定がほとんど改正されていないこと
1922年(大正11年)に制定されたいわゆる大正刑事訴訟法は、ドイツの影響を強く受け、裁判所による職権主義的規定が多く採用された。しかし戦後、米国GHQの統治下において日本国憲法が制定され、1949年1月1日、現行刑事訴訟法が施行されると、起訴状一本主義や検察官・弁護人の証拠調請求権などを例とする当事者主義的規定が採用されることとなった。これにより、検察官・裁判官と弁護人が対立するという職権主義的訴訟構造(糾問主義)は見直され、裁判官・検察官・弁護人がそれぞれの立場で刑事手続に関与する当事者主義的訴訟構造(弾劾主義)へと日本の刑事手続は転換した。
しかし、「第四編 再審」は、不利益再審の禁止を除けば、戦前の職権主義が妥当する旧刑訴法の規定がほぼそのまま踏襲されている。証拠調べを含む審理手続に関する規定は事実の取調べに関する刑事訴訟法445条のわずか一条のみである。
⑵ 証拠開示が再審手続の審理に与える影響は極めて大きいこと
2004年(平成16年)の刑事訴訟法改正によって現在の証拠開示制度が創設される以前は、証拠開示に関する明文規定はなく、個別の事案において裁判所が訴訟指揮権に基づき証拠開示を命じるという運用がなされていた(最高裁昭和44年4月25日決定・刑集23巻4号248頁)。
刑事訴訟法435条6号は、再審請求の要件として、新証拠に基づくものであることを要求する。この新証拠は、再審請求審における証拠開示によって捜査機関の手持ち証拠の中から得られることが多く、裁判所による証拠開示の運用は、再審請求審及び再審公判の結論を左右するほど核心的な役割を果たしてきた。
例えば、日野町事件では、裁判所の勧告を受け、第1次再審で公判未提出の証拠の一覧表が開示された。さらに第2次再審請求審で、裁判所の主導によって写真のネガを含む多数の手持ち証拠が開示された。その中にネガフィルムがあり、このネガフィルムに記録された写真の撮影順と、確定審で有罪の決め手となった金庫引当調書に添付された写真の順番が異なっていたことがわかった。これにより、被疑者が金庫発見場所への道中を案内する往路の場面を撮影した写真が、捜査の帰路(復路)に撮影されたものであること等の事実が発覚した。
そのため、引き当たり捜査で秘密の暴露を行ったという自白の信用性を支える前提事実が崩れることとなり、再審開始に大きな影響を与えた。
また、袴田事件では、第1次再審請求審では全く証拠が開示されなかったが、第2次再審請求審で裁判所が証拠開示を勧告し、約600点余りの証拠が開示された。その中に、確定審で有罪の決め手の一つとされた、犯人が着ていたとされる「5点の衣類」を撮影したネガが含まれていた。このネガを改めて現像したところ、発見直後の衣類に付着した血痕の色が、不自然なほど赤いことがわかった。弁護側は、1年2か月もの間味噌樽に投げ入れられた場合、衣類の血痕は全く赤みが残らないことを再現実験で示し、再審開始決定に大きく結びついた。
湖東記念病院事件では、再審公判になって検察庁に送致されていなかった捜査報告書が開示された。その内容は、捜査段階で解剖医が、被害者の自然死の可能性を指摘するというものであった。
これを受け再審公判を担当した大津地裁の裁判官も、無罪判決を言い渡した後、「逮捕から15年以上経って、初めて開示された証拠もありました。西山さんの取り調べや証拠開示など一つだけでも適切に行われていれば、西山さんが逮捕・起訴されることもなかったかもしれません。」等と述べた。
このように、再審手続における証拠開示は、多くの再審事件において重大な意義を有してきた。
⑶ 再審格差
2001年、司法制度改革推進法が成立してから、いわゆる刑事司法制度改革が着々と進み、公判前整理手続、被疑者国選弁護制度、証拠の一覧表交付制度、取調べ全体の録音録画など、被疑者・被告人の刑事手続における手続的正義の充実に資する法改正が続いている。
ところが、再審手続に関する規定は、70年以上に亘り一度も改正されず、職権主義的規定のみを残す状態で現在に至っている。
そのため、再審手続に関しては特に法整備が遅れていると評しても過言ではなく、実際に再審事件を担当し職権を行使する裁判官ごとに審理の充実度合いが異なる、いわゆる「再審格差」という事態が生じている。
例えば、大崎事件では、第2次即時抗告審(福岡高裁宮崎支部)及び第3次請求審(鹿児島地裁)で証拠リストも含めた213点の証拠が開示されたが、第2次請求審(鹿児島地裁)は全く証拠開示に向けた訴訟指揮を行わずに請求を棄却した。
このように、現状の再審手続を通覧すると、証拠開示勧告や証拠開示命令を行う裁判体、全く証拠開示に関する措置を講じない裁判体が混在しており、無辜の発見が再審を担当する裁判官の裁量に大きく左右されているという重大な問題がある。
そこで、証拠開示に関する規定を設け、適切に捜査機関の手持ち証拠を開示させる必要性が高い。
⑷ 海外の諸制度
国外の先進国の再審手続においても、証拠開示に関する定めをおく国は多い。
例えば、フランスでは、再審請求者に対し、再審請求前に、捜査機関の手持ち証拠の開示を請求する権利を付与している。これを受けた検察官は、理由を付した決定書によって回答しなければならない。
ドイツでは、弁護人に記録閲覧権が与えられており、これは通常審・再審にも共通に適用されるため、再審においても当事者の権利として証拠開示を実現できる。
台湾でも、2019年に刑事訴訟法が改正され、ドイツと同様に通常審・再審の区別なく弁護人が証拠にアクセスできる「記録情報獲得権」が設けられた。
アメリカのワシントン州では、判決後すべての証拠・事件記録が公的記録とされ、州の情報公開法により誰でも州に対して開示を請求できる。また、テキサス州では、2013年に成立した「マイケル・モートン法」によって、検察官に全証拠の開示が義務付けられている。
このように、再審手続における証拠開示規定の設置は、国際的にも主流になっていると評価しうる。
2 検察官の不服申立てを許容する規定の存在
⑴ 刑事訴訟法450条
刑事訴訟法450条は、「第446条、第447条第1項、第448条第1項又は前条第1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と定めている。したがって、再審請求棄却決定(刑訴法446条、447条)、再審開始決定(刑訴法448条)のいずれにも即時抗告できる規定ぶりとなっている。
そのため、検察官が再審開始決定に不服を申し立て、本案であるはずの再審公判が開始されるまで極めて長期化するという問題が生じている。
⑵ 具体例
1961年(昭和36年)に起きた名張毒ぶどう酒事件では、第7次再審請求審で再審開始決定が下されたが(2005年(平成17年))、即時抗告審において再審開始決定が覆され、その後第9次請求審の審理途中である2015年(平成27年)に、再審請求人である奥西勝氏は89歳で死亡した。事件発生から54年の歳月が経過していた。
袴田事件は1966年(昭和41年)に発生し、2014年(平成26年)、第2次請求審(静岡地裁)で再審開始決定が下されたが、検察官による即時抗告がなされ、再審開始決定が確定した2023年(令和5年)まで、57年余りが経過し、袴田巌氏は現在87歳となっている。
大崎事件は第1次、第3次で再審開始決定がなされたが、検察官の不服申立てがなされ、現在も係争中であり、原口アヤ子氏は現在96歳を迎えている。
このように、再審手続開始に至るまでの長期にわたる審理の過程で、ほとんどの再審請求人は刑務所内で過ごすことを余儀なくされ、甚大な肉体的・精神的苦痛を被っている。
また、審理の長期化のため無罪を獲得することなく死亡してしまう事例も珍しくなく、かかる事態は人権擁護の観点から深刻な課題を有するものといわざるを得ない。
⑶ 改正の必要性
そもそも、日本における戦前の刑事訴訟法では、被告人の無罪判決が確定した後も有罪を巡り検察官が再審請求をすることを許容する、いわゆる不利益再審を認めていた。
しかしながら、戦後の日本国憲法39条において「既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」と定められ、無罪の判断を受けた者への再度の訴追を禁じるいわゆる二重の危険の禁止規定が設けられた。これにより不利益再審が廃止され、再審の目的は唯一「無辜の救済」のみとされた。
したがって、再審手続の要件は緩やかな解釈が要請され、その速やかな開始が憲法的に要請されていると解するべきである。
また、検察官は「公益の代表者」(検察庁法4条)であり、いたずらに有罪のみを追い求める司法機関ではない。利益再審のみが認められた前述の趣旨を踏まえ、無辜の救済のために裁判所の審理に協力する立場にあるから、再審開始決定を下した裁判所の立場を尊重し、これに対する不服申立てを行わないよう法が要請することは、検察官の立場にむしろ整合するものである。
かく解しても、再審制度は、再審請求審と再審公判という、二段階の手続が予定されており、検察官の有罪の主張は再審公判で行うことも可能であるから、何らの弊害もない。
したがって、再審手続開始決定に対する検察官による不服申立ては、本来これを禁止すべきものであり、その旨の改正がぜひとも必要であるというべきである。
⑷ 諸外国の制度状況
現行刑事訴訟法の再審規定(同法435条ないし453条)は、戦前のドイツ法に倣った職権主義を基調とするものであるが、そのドイツでも、1946年に立法でもって再審開始決定に対する不服申立てを禁止している。
英米法圏の各国では、通常審においても一般的に検察官による上訴を認めていない。また、フランスでも、審理委員会の付託を経て裁判構成機関が再審・再審査請求に理由があると判断したときは、言い渡された有罪判決を取り消すこととし、この取消決定に対する不服申立てはできないとされている。
したがって、不服申立て制度の撤廃は国際的な流れにも沿うものである。
第3 結語
国家における刑事司法手続は、人間が運営する以上、完全なものでは決してあり得ない。何ら落ち度のない無辜の者の生命・自由を、我々の手で奪い去ることは、人間が為す最大の過ちの一つといっても過言ではない。
過去幾度に亘りえん罪が発生し、無辜の者を処罰した反省を踏まえ、再審手続においても「疑わしきは被告人の利益に」という近代国家の鉄則を制度的に実現し、人権保障を貫徹すべきである。
以上の次第で、当会は再審手続の改正を求める。
以上