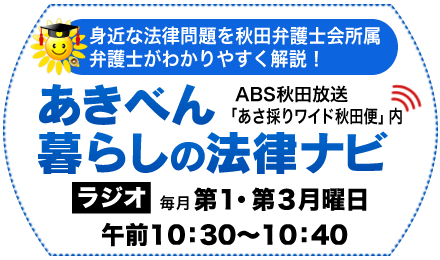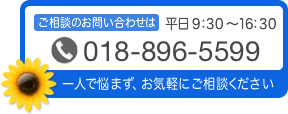少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明
1 平成27年6月17日に公職選挙法の一部を改正する法律が可決・成立し,選挙権年齢が18歳に引き下げられることになった。同法附則11条は,「民法,少年法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする」と定めており,少年法の適用年齢について,18歳に引き下げる方向での議論が進められている。
しかしながら,選挙権年齢と少年法の適用年齢を法的に一致させなければいけない必然性はない。たとえば,現行民法は,行為能力を認める年齢として,「20歳をもって成年とする」と定めているが,身分行為である養子縁組行為や遺言能力は15歳で認めており,制度の目的や子どもの判断能力により適用年齢を区別している。さらに,喫煙や飲酒は20歳を区分年齢としているが,パチンコ店の入店は18歳,サッカーくじの購入は19歳を区分年齢としており,子どもの成熟度を考慮した年齢区分がなされることもある。
したがって,少年法の適用年齢を18歳に引き下げるべきかどうかは,「成年年齢を18歳と定めた」という理由で単純に決せられるものではなく,18歳,19歳の者による犯罪の現状,その者の成熟度,現行少年法制が果たしてきた役割を踏まえた上で,犯罪予防や更生の仕組みなど社会全体の利益の視点から,詳細かつ具体的に検討し,決せられるべきである。
2 この点,年長少年(18歳以上20歳未満の少年)の,平成25年における一般刑法犯検挙人員の総数は1万1234人であるところ,罪名別に見ると,殺人20人(0.2%),強盗192人(1.7%),強姦56人(0.5%),放火18人(0.2%)など凶悪犯罪が占める割合は成人と比べて極めて低く,窃盗5320人(47.4%),遺失物等横領2681人(23.9%)など,大半は比較的軽微な犯罪で占められている。
現在は大学進学率が向上したことなどもあって,18歳,19歳になっても経済的に自立できる年長少年は多くなく,社会経験も豊富とはいえない場合が多い。また,若年層は,未だ人格形成の途上にあり,対人関係を構築するのが不得手なこともあり,他者に共感する感情や想像力に乏しい場合も見られる。
これまでの少年法制では,保護主義の見地から年長少年の事件については,全件家庭裁判所に送致するものとし,必要に応じ観護措置決定を行い,鑑別所や家庭裁判所調査官により専門的科学的知見に基づいて少年の行動鑑別,心理鑑別を行った上で,審判を行い,個々の少年の要保護性に応じた処分を行ってきた。その趣旨は,このような若年者の犯罪の特徴を踏まえると共に,特に非行少年の場合,家庭で虐待を受けていたり,学校や地域で疎外されていたりするなど,自らの力ではどうにもならない事情により厳しい環境に置かれるケースも見られること,他方で若年者は未だ人格形成の途上にあって,可塑性に富み,犯罪傾向は進んでいないことが多いことから,犯罪の軽重だけではなく,少年の課題に沿った対応を行い,その立ち直りの機会を与えるためであった。
3 仮に,少年法の適用年齢を引き下げることとすると,比較的軽微な罪を犯した18歳,19歳の者の資質・環境上の問題点が十分に解消されないまま,大半が起訴猶予により何らの対応もなされないまま社会に戻ることになり,問題点を一層増幅させ,重大な犯罪に発展させかねないケースも生じかねない。さらに,若年者が実名報道され,起訴猶予されずに公開の裁判にさらされた上で,前科者となることもあり,その結果人生の早い段階において将来における就職等の機会を失わせてしまい,更生の機会を奪う結果にもなりかねない。
なお,現行の少年法下においても,16歳以上の少年が故意に人を死亡させた場合には,原則として検察官に送致され,成人と同じ刑事手続により処罰されるのであり,18歳以上であれば死刑の言い渡しを受ける場合もあり,少年法の適用があるからといって,重大事案への対応ができないということはない。
4 以上のとおり,成人年齢の引き下げがなされたとしても,人格形成途上の若年者の犯行であるということについては何ら変わりがなく,これまで少年法が対象としてきた,個別の事案に応じた保護処分を中核とする対応の必要性については全く変わるものではない。このような実態を踏まえずに,少年法の適用年齢を一律に引き下げることは社会全体の利益という視点からも相当とは言い難く,少年犯罪の実情の把握が欠けており,有効に機能している少年法制を理由もなく覆すものにほかならない。
よって,当会は,少年法の適用年齢の引下げに強く反対するものである。
2015年(平成27年)7月29日
秋田弁護士会
会長 京 野 垂 日