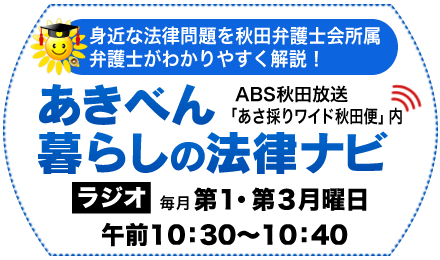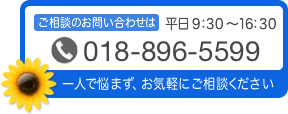金融庁に対する貸金業規制法施行規則及び事務ガイドラインの一部改正に関する意見書
2005年8月25日 公開
2005年8月25日
金融庁長官 五 味 廣 文 殿
秋田弁護士会
会長 面 山 恭 子
意 見 書
当会は,以下のとおり,貸金業規制法施行規則17条1項の改正を求めるとともに,金融庁が本年8月12日付けで公表し,意見募集を行っている事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)の一部改正について,意見を述べる。
第1 意見の趣旨
1 貸金業規制法施行規則17条1項の改正について
同条項を改正して,「貸金業者は,貸金業規制法19条の帳簿(当該債務者と最初に貸付をした時点から全て)を当該債務者が最後に弁済した日から少なくとも10年間は保存しなければならない。」とすべきである。
2 ガイドライン3-2-2関係について
(1) 同(6)の改正案として,「顧客,・・・(中略)・・・又は顧客等の代理人が,弁 済計画の策定,債務整理その他正当な理由を示した上で貸金業者に取引履歴の開示を求めた場合において,これを拒むこと又は虚偽の回答を行なうこと」が示されているが,「債務整理」と「その他正当な理由」との間に「,不当利得返還請求」との文言を追加すべきである。
(2) 新たに同(9)として,「顧客等から受けた弁済について貸金業規制法43条1項の適用がない場合に,顧客等に対し,利息制限法所定の制限利率による充当計算を行なった後の残存債務額よりも過大な請求をし,あるいは,不当利得返還債務の履行をしないこと」を追加すべきである。
3 ガイドライン3-2-8(1)関係について
顧客等の代理人である弁護士が開示の求めをする場合には,「債務者が債務の処理を弁護士に委託した旨の弁護士からの書面による通知」(貸金業規制法21条1項6号参照)が送付されていれば(ファクシミリによる場合を含む),本人であること及び本人との委任関係の確認として十分かつ適切であるとすべきである。
第2 意見の理由
1 貸金業規制法施行規則17条1項改正について
(1) 貸金業者が保存している帳簿は,顧客の貸金業者に対する残存債務額や不当利得返還請求額を確定するために最も重要な証拠資料である。そして,貸金業者が正確な帳簿に基づいて正しく取引履歴を開示することは,貸金業者と顧客との紛争の予防・解決に必要不可欠の前提であって,顧客の利益保護に適うものである。そればかりか,貸金業者が正しく取引履歴を開示することによって,短期的には不当利得返還債務額の増大などの不利益を被ったとしても,全ての取引履歴を正しく開示する公正な態度によって国民の貸金業者に対する評価が高まれば,貸金業界の健全な発展に資するものと考えられる。
(2) 最高裁判所第三小法廷平成17年7月19日判決は,貸金業者が「貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う」との判断を示したが,このような判断がなされたのは,前述したとおり,帳簿及びこれに基づく取引履歴開示が貸金業者と顧客との紛争の予防・解決にきわめて重要な役割を果たしているからであるのは言うまでもない。ところが,遺憾ながら,一部の貸金業者は,現行の貸金業規制法施行規則17条1項に基づく3年間の帳簿保存期間を自己に有利に限定的に解した上,個別の貸付債権が消滅してから3年間が経過すれば,次々に帳簿を廃棄したり,あるいは,廃棄してしまったと主張したりして,顧客との取引履歴を不明朗化することにより,利息制限法に基づく残存債務額の確定や不当利得返還請求権の行使を困難にしようとしている。
しかし,最高裁は,帳簿に基づく取引履歴開示義務は保存期間を経過した帳簿にも及ぶものと判断している。貸金業規制法施行規則17条1項や商法上の帳簿保存期間を経過していたとしても,貸金業者と当該顧客との間の取引の全てが明らかにならなければ,当該紛争が適正に解決できないことからすると,当然の判断である。
そうすると帳簿の保存期間については,現行規則の3年間では短きに失しており,少なくとも顧客の業者に対する最後の弁済の日から10年間(不当利得返還請求権の消滅時効期間)としておくことが妥当である。
(3) また,帳簿の保存期間の起算点は,個別の債権が消滅した日とするのではなく,顧客が最後の弁済をした日からとすべきである。
この点,包括契約に基づき貸付及び弁済が複数回反復される場合,借換えが何度もなされる場合,貸金業者と顧客との長年にわたる取引の間で数日から数年間も取引が中断する場合については,個別の貸付ごとに帳簿の保存義務や期間を考慮するとの考え方もありうる。しかし,裁判実務上は,包括契約に基づく貸付はリボルビング契約であれば一個の契約とみなされているし,複数の契約と判断される場合も利息制限法上の計算は一体として取り扱う例が多い。また,借換えについては借換えの前後を通じて一個の契約と判断されている。取引が中断した場合でも,中断前の取引で発生した過払い金を中断後の貸付に充当するなどして通算して過払い金を計算する取り扱いが多い。このような裁判実務上の取り扱いからすると,貸金業者と顧客との紛争を解決するためには,当該顧客が最終弁済をした日から10年間(不当利得返還請求権の消滅時効期間)が経過していない限り,貸金業者が当該顧客と最初に取引をしたときからの全ての帳簿を保存しておく必要性が顕著である。
このように帳簿の保存期間の起算点を個別の債権が消滅した日ではなく,顧客が最後に弁済した日からを基準にし,かつ,貸金業者をして当該顧客と最初に取引をしたときからの全ての帳簿を保存させておくことは,貸金業規制法19条が貸金業者に対し顧客ごとに所定の事項を記載した帳簿を備え付けることを求めている法の趣旨にも適う。
2 取引履歴開示義務違反が行政処分の対象となることの明確化(ガイドライン3-2-2関係)について
(1) 「貸金業者に取引履歴の開示義務があり,正当な理由に基づく開示請求を拒否した場合には行政処分の対象となり得ることを明確化する」との改正の趣旨には賛成である。
最高裁判所第三小法廷平成17年7月19日判決は,貸金業者が「貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う」との判断を示した。
この最高裁判決を受けて,金融庁がこのたびガイドラインを改正して貸金業者が取引履歴開示義務に違反して開示請求を拒否した場合には行政処分の対象となり得ることを明確化することは,妥当である。
しかし,上記最高裁判決は,債務者が債務内容を正確に把握出来ない場合には,「弁済計画を立てることが困難になったり,過払金があるのにその返還を請求できないばかりか,更に弁済を求められてこれに応ずることを余儀なくされるなど,大きな不利益を被る」ことなどに鑑みて,取引履歴開示義務が存在するとの結論を導いている。
そうである以上,改正案のうち,事務ガイドライン3-2-2にいう取引履歴開示請求の「正当な理由」として「弁済計画の策定,債務整理」だけを例示し,「過払金の返還請求」について殊更に言及を避けているのは,不適切である。「過払金の返還請求」も,取引履歴開示請求の正当理由のうちに含まれることを明記すべきである。
(2) また,最高裁第二小法廷平成16年2月20日判決は,貸金業規制法43条が適用される要件を厳格に解釈し,例えば,貸金業規制法17条1項に規定する書面に該当するためには,当該書面に同項所定の事項のすべてが記載されていなければならないとするなど,明確な判断を下している。貸金業者においては,当該顧客から受けた弁済について,貸金業規制法43条の適用条件を満たしているかどうかは,容易に判断できるものであり,現に,貸金業者が顧客に対し裁判上の請求をする場合には,利息制限法所定の制限利率により充当計算をした後の残存債務額を訴状の請求の趣旨に記載している実情にある。
ところが,貸金業者が裁判外で顧客等に対し支払を求める場合は,貸金業規制法43条が適用されないことを承知であっても,利息制限法所定の制限利率により充当計算した後の残存債務額よりも過大な請求をしており,ひどい場合には,利息制限法上過払いであることを承知の上で顧客等に対し返済を求めることが常態化している。
利息制限法所定の制限を超過した支払は,そもそも無効であって,貸金業規制法43条が適用される場合に限って事後的に有効とされる場合があるが,同条のみなし弁済が適用されることの主張立証責任が貸金業者に課されていることからしても,貸金業者には,同条のみなし弁済が適用されるかどうかを的確に判断した上,もし適用されない場合には,利息制限法の範囲内の請求に止めておき,過払いとなった場合は速やかにこれを顧客に返還しなければならない。これを怠った場合には,債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり,偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いたものに該当するおそれが大きいものと例示すべきである。
3 取引履歴開示請求の際の本人確認手続きの明確化(ガイドライン3-2-8関係)について
(1) ガイドライン改正案は,本人確認書類及び委任関係を示す書類について,①金融機関等による顧客等の本人確認及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下,「本人確認法」という)が規定する本人確認書類や②当該顧客等の署名及び捺印により委任関係が示されている書類等の提示を要求している。
これを現実に当てはめてみると,弁護士が顧客等から債務整理の委任を受けた場合,通常,数社から数十社の貸金業者が相手方となるが,全国各地に散在する多数の貸金業者に対し,本人確認書類として運転免許証等の原本を提示することは不可能であり,運転免許証等の写しを送付することになる。この場合,貸金業者に本人確認書類として印鑑登録証明書を送付などすれば,どのように悪用されるか不安があり,そのようなリスクを冒すことはとてもできないであろう。
次に当該顧客等の署名及び捺印により委任関係が示されている書類を提示することになるが,前述のように本人確認書類を写しで提出した場合,印鑑登録された印鑑か契約書に捺印した印鑑により委任状等に捺印する必要があることになる。しかし,通常,顧客は多数の貸金業者との取引をしているので,契約書に捺印した印鑑がどれか記憶がないことが多く,その場合は,印鑑登録された印鑑で捺印することになる。結局のところ,その印鑑が印鑑登録されていることを証明するためには印鑑登録証明書を添付せざるを得ないことになるが,貸金業者の中には添付した印鑑登録証明書を悪用する者がないとは言えないので,安易に印鑑登録証明書を貸金業者に送付することはできない。
また,このような手続が現実になれば,印鑑登録証明書等の申請費用と手間が必要になる。債務整理を必要とする多重債務者はそもそも経済的に困窮している状態にあり,このような書類の入手手続などに不慣れであることが多い。このため,それらの費用負担が履歴開示請求の意思を挫くことにもなりかねない。また債権者数に応じて何枚もの委任状に署名を求めるのは,迅速な事務処理が必要とされる債務整理の実情に合わない。
このようにガイドライン改正案が例示する手続は,煩雑な書類の提示を条件とするものであり,現在の実務慣行とかけ離れており,妥当ではない。その結果,顧客等がこのように煩雑な手続に応じられないことをもって,貸金業者が取引履歴開示を拒否する口実となりかねない。むしろ,取引履歴の開示を求めることは顧客等の権利であって,本人確認の手続に伴う負担が顧客等による開示請求権の行使を妨げることのないよう,貸金業者に対して注意を喚起すべきである。
(2) ガイドライン改正案は,本人確認等の方法として本人確認法による手続に準拠しており,同法は,テロ及び組織犯罪等の悪質な犯罪行為に対する資金提供のために金融機関等の預金口座が不正利用されることを防止する目的で,厳格な本人確認の手続を定めたものである(同法1条)。しかし,取引履歴開示請求や過払金返還請求が「テロ及び組織犯罪等の悪質な犯罪行為に対する資金提供のために」悪用されているという社会的事実は,およそ存在していない。したがって,規制の目的・対象がまったく異なる本人確認法の定める確認方法を持ち込むことは,誤りであるといわざるを得ない。
他方,貸金業者が本人確認を十分に行わず取引履歴を第三者に開示して過払金を払ってしまい,このために顧客等以外の権利が侵害されているというような弊害は,起こる余地もないことである。金融機関が保有する顧客情報が大量に盗まれるという近時多発するトラブルとも別問題であることはいうまでもない。したがって,現在必要なのは,取引履歴開示に応じる際の本人確認手続の「厳格化」ではない。現在起きているトラブルは,ごく一部の貸金業者が,「個人情報保護法に基づく本人確認手続」に名を借りて,自らが一方的に定めた確認手続に応じなければ取引履歴開示ができないとして開示を拒否する口実にしようとしている,ということである。したがって,現在必要なのは,取引履歴の開示請求権は顧客等の権利であって,取引履歴開示を回避するための口実として本人確認手続を利用してはならないことを「明確化」することである。
(3) 個人情報保護法は,個人情報取扱事業者が本人からの保有個人データの開示の求めに応ずる手続を定めることができる(同法25条1項,29条1項・3項・4項)とするが,「他の法令の規定により開示することとされている場合」(同法25条3項)を除外している。しかるに前掲最高裁判決は,取引履歴開示義務の法的根拠が信義則(民法1条2項)にあることを明らかにした。したがって,個人情報保護法25条3項により,貸金業者が定めた本人確認の手続によって顧客等を一方的に拘束することはできず,この手続に応じないことをもって取引履歴開示請求を拒む正当理由とすることはできない。また,個人情報保護法は,同法に基づき個人情報取扱事業者が開示等の求めに応じる手続を定め得る場合についても,「本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない」(同法29条4項)と定めている。個人情報保護法の存在が,自己に関する情報にアクセスする個人の権利を阻害する結果を招いてしまうのでは,本末転倒だからである。
(4) 債務整理の実務においては,「債務者が債務の処理を弁護士に委託した旨の弁護士からの書面による通知」(貸金業規制法21条1項6号参照。以下,「受任通知書」という)が債務者の代理人であることの十分かつ適切な確認資料として確立している。実際,多くの貸金業者は,個人情報保護法が施行された現在においても,弁護士が作成名義人である「受任通知書」の送付をもって代理権確認の方法とすることを,従前通り異議なく認めている。
弁護士に依頼する多重債務者は一日も早く受任通知書を送付して,貸金業者からの直接の取立行為がない状態にする必要に迫られていることがほとんどであり,受任通知書の送付による実効性の発揮は極めて重要である。
弁護士名の「受任通知書」を信頼したために貸金業者が不正な開示請求に応じてしまったというトラブルが発生しているわけでもない。あたかも弁護士と顧客等との委任関係の存在が疑われる状況が広く存在していることを前提とするかのように,厳格な手続を課するのは正当ではない。万一,弁護士が受任通知書で自らの氏名を明らかにした上で自ら不正な開示請求などを行ったりすれば,弁護士職務基本規程違反行為として懲戒処分を受けるという重大な不利益を受けることになるのである。
(5) 以上により,顧客等の代理人である弁護士が開示の求めをする場合には,「債務者が債務の処理を弁護士に委託した旨の弁護士からの書面による通知」(貸金業規制法21条1項6号参照)が送付されていれば(ファクシミリによる場合を含む),本人であること及び本人との委任関係の確認として十分かつ適切であるとすべきである。
以上